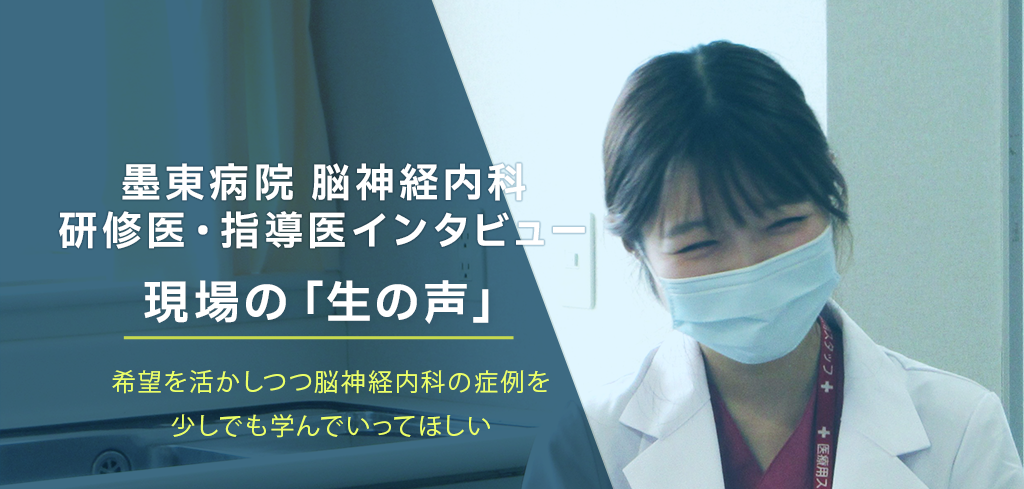
墨東病院を選んだ理由、どこに惹かれたかを教えていただけますか?
研修医 S: 初期研修のうちは救急が強い病院に行きたいなと大きく探していて、その中での診療科が揃っていて、後期研修の枠もある墨東病院が選択肢になりました。
研修医の先生がスキマ時間などをうまく使って勉強されていて、前向きな向上心をもつ雰囲気に惹かれ志望しました。

研修医 M: 私は一年目だけここにいて、来年は大学病院に移るという『たすき』と呼ばれるプログラムを利用しているのですが、三次救急病院で救急症例も多く集まり、内科のローテーション中もいろんな症例を診れるのではないかという期待で一度見学も来ました。
その時の研修医の先生方がすごく優しく接してくれたのと、先生同士で症例のことを話してたり積極的に学んでいる人が多いという印象があったので希望しました。
脳神経内科の主な疾患や病態について教えていただけますか?
研修医S:脳梗塞など虚血系の疾患はもちろん、変性疾患や筋炎などで動けなくなってしまった方など様々な方がいらっしゃいます。
研修を進めていく中で、指導医との関わり方はいかがですか?
研修医 S:やはり一年目で、まだ診療の流れや病院のシステムがわかっていないことが多々あるのですが、そういうところはちゃんとサポートしていただけます。いろいろと検査などを提案してみて、思った以上に「やっていいよ」と言ってくださることが多くて、勉強になります。
指導医 M: 神経内科の指導医としては、科の特性で比較的経過が長い患者さんが多いので病歴をしっかり取れるようにしてほしいという思いは常にあります。
研修医は救急をしたいという方が多く、そういう希望を活かしつつ脳神経内科の症例を少しでも学んでいってほしいです。
患者さんを診る上で、気をつけていることはありますか?
研修医 S:全体的に、他科でもそうですが、医療者と患者さんの間で捉え方が違うということがよくあると思っています。病気に対して患者さんがどういう考えを持っているのか、医療者側がどうい報を出すのかということが、患者さんにとっては大きなことだと思っています。 そういったバックグラウンドの差を考慮しながら、自分の考えていることを伝えるようには気をつけたいですね。

研修医 M:やはり脳梗塞は突然起こることが多いため、患者さんが突然話せなくなったり、手が動かなくなったりします。ご家族の方にとってはたった一人の家族が病気になっている状況だと思うので、患者さんやお話している相手がどんな方なのか、どういう思いでいらしたのか、そういったことも含めながら、話し方や話すスピードなどにも気を配ることが大事なのだろうと感じました。
研修医の先生方がどう接していいか悩まれている時、指導医の先生からアドバイスは?
指導医 M: 私に関して言うと、あまり押し付ける形のやり方はしないようにはしています。
大事なことは、その患者さんと家族の方を尊重する、医療者と立場は違うけれども、という点を大事にしてほしいなと思っています。
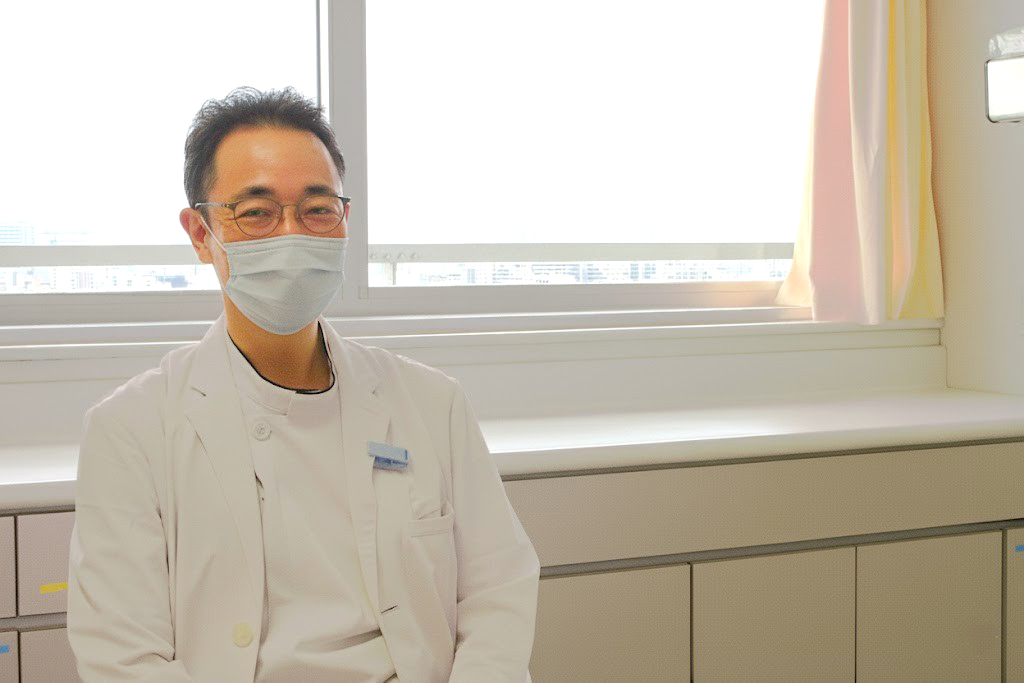
学生時代の時に思い描いていた研修医の生活と実際の生活、違うところはありますか?
研修医 S:そうですね。僕の場合はあまり変わってはいないですね。楽しく過ごせています。
研修医 M:学生時代は見学など外から見ている気持ちが強かったのですが、研修医になってチームの一員になれている感覚があって、そういった意味では期待通りです。今、チームの一員として自分の役割があることが、とても嬉しく思います。

研修医や医学生向けに墨東に興味を持っている医学生に対して一言!
研修医 S: 墨東病院の良さだと思っているのが、縦の繋がりが強いことです。色々な年次の先輩方が親身になって教えてくれるっていうのはすごく貴重なことだと思うので。ぜひ、見学来ていただいて、体感していただければなと思います。
研修医 M:どの科でも先生方が丁寧に指導してくださり、こちらから積極的に質問していけばいくほど、先生方もたくさん教えてくださいます。
何科を志望しているにしても、墨東病院はとても成長が望める環境だと思います。
指導医 M:脳神経内科としては、市中病院ですと脳梗塞の症例がほとんどを占めることが多いですが、当院では脳梗塞は半分以下で症例はバリエーションが豊富です。
脳神経内科を目指している方でも充分に満足できると思いますので、興味のある方は是非見学にいらしてください。



